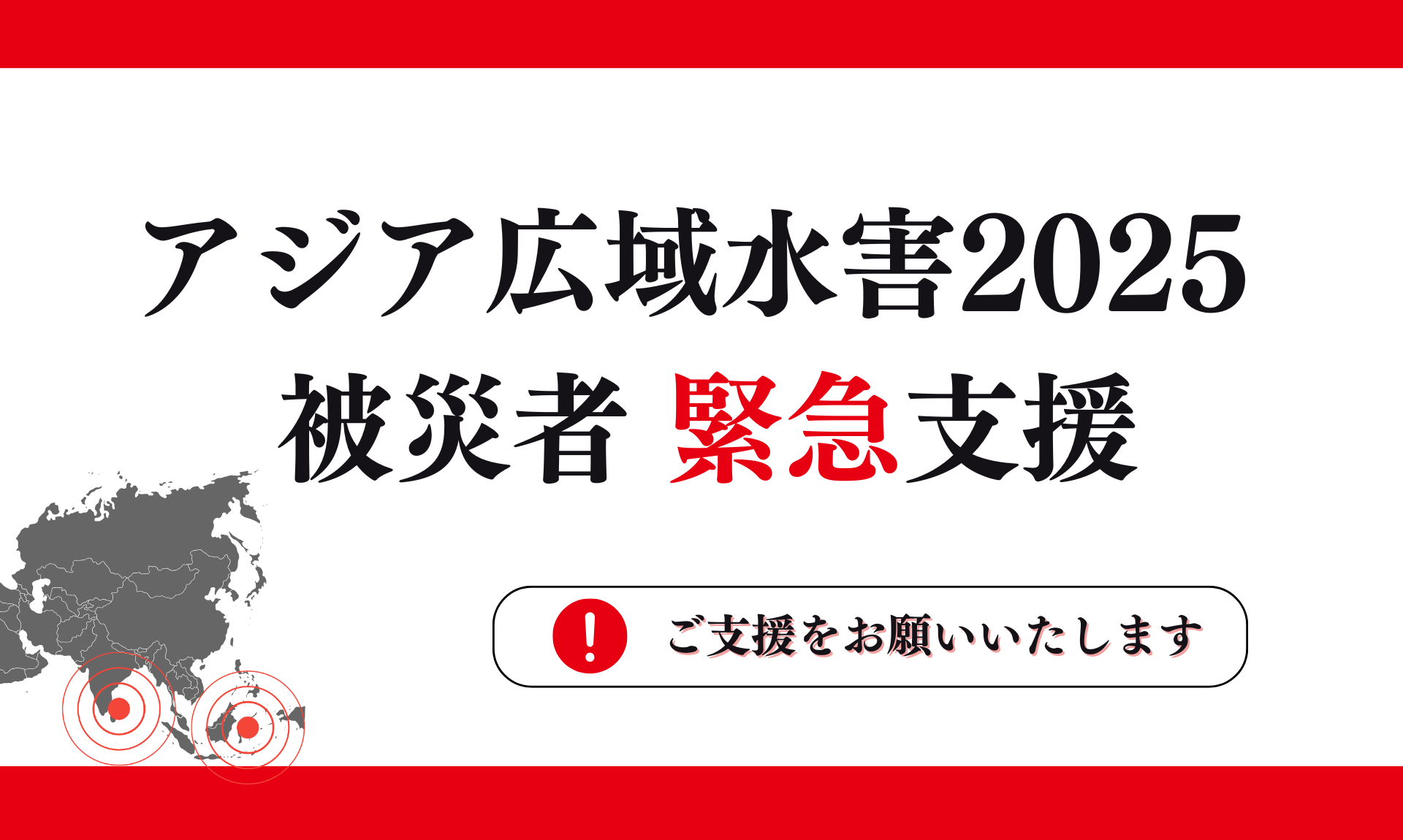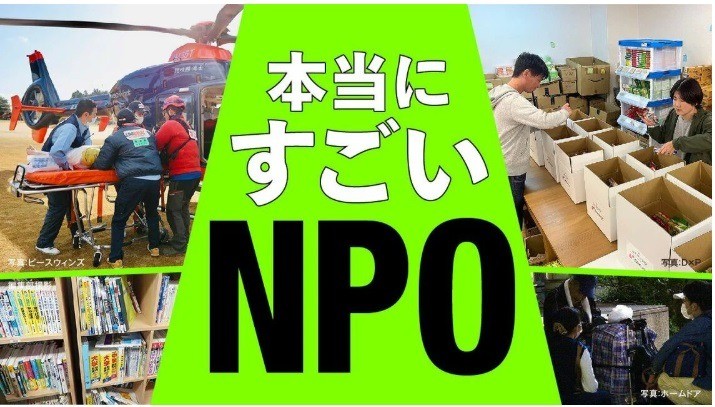3/12 第3回 企業×NGOミートアップ 「持続的パートナーシップで考える、企業×NGO連携の未来」 開催のお知らせ
人が集まり、またつながる場所へ 能登町「なごみプロジェクト」
ジャパン・プラットフォーム(JPF)
人が集まり、またつながる場所へ 能登町「なごみプロジェクト」

「なごみ」施設内には、解体予定の家屋から取り出した「もったいないコーナー」も/鳳珠郡能登町/2025.10.21 ©JPF
ジャパン・プラットフォーム(JPF)は、能登半島で発生した地震および豪雨被害に対し、現地で築いてきたネットワークと加盟NGOの多様な専門性をいかしながら、現在も支援を継続しています。
地震からまもなく2年、豪雨から約1年が経過したタイミングで、現地の状況と今後の課題を改めて直接確認するため、JPFスタッフは2025年10月21日に鳳珠郡能登町を訪問しました。
2024年1月1日に石川県能登地方で発生した震度7の地震を受け、JPFでは、当日のうちに加盟NGOによる緊急支援・現地ニーズ調査開始を決定、出動しました。
加盟NGOのパルシック(PARCIC)は、1月6日にスタッフ2名を石川県に派遣し、珠洲市に支援物資を届けるところから支援をスタートしました。
PARCICでは、被災の影響により営業を停止していた能登町にある「能登七見健康福祉の郷 なごみ」の一部を借り受け、地域を越えて人々が集う期間限定の交流拠点を運営しています。ここを中心に、能登町に暮らす被災者の居場所づくりや、親子を対象とした支援を続けています。
現地で活動にあたるPARCICの国内事業担当 小栗清香さんに、「なごみ」開設の経緯や、現在の取り組み、地域住民との関わりについて伺いました。
 支援活動を続ける中で、震災後の地域では、かつて同じ地区で生活していた人々が、仮設住宅や在宅、町外のみなし仮設といった、異なる住まい方によって分かれ始めている状況が見えてきました。
支援活動を続ける中で、震災後の地域では、かつて同じ地区で生活していた人々が、仮設住宅や在宅、町外のみなし仮設といった、異なる住まい方によって分かれ始めている状況が見えてきました。
仮設住宅の集会所には仮設入居者だけが、公民館でのサロンには在宅被災者だけが集まるなど、交流の場が住環境ごとに分断されつつあったのです。
また、町外に避難している人からは、「戻っても集まる場所がない」「情報が届きにくい」という声も聞かれました。
能登町内には公民館自体は多くありますが、地区を越えて人が集える場所はほとんどありませんでした。
そこで、プールとお風呂が併設され地域の人にとって集う場であった「なごみ」を、場所や状況の違いを越えて再びつながりを取り戻せる場として開こうという動きが生まれ、「なごみプロジェクト」が始まりました。
しかし、被災した施設を交流拠点とするためには大規模な修繕が必要で、とくに停止していた高圧電気の再開に伴う工事や仮設浄化槽の設置には多くの時間がかかりました。最初に施設を見学してから再稼働の見通しが立つまでに約半年を要し、ようやく2025年2月に「なごみ」は再び人々を迎える憩いの場としてオープンすることができました。
再開後も、空調施設を整えるなど整備が必要でしたが、徐々に快適な環境が整えられ、にぎわいが戻ってきています。
週5日営業しているカフェ「ちょっこりカフェ『なごみ』」は「ランチがおいしい」と評判で、地域の人が気軽に立ち寄る場になっています。
また、月1回開催しているこども食堂では、前回の開催時には約130名の参加があり、その半数が18歳以下の子どもたちでした。回を重ねるごとに参加者が増え、食器が足りなくなるほどの盛況ぶりです。
 「なごみプロジェクト」の話を伺っている様子/鳳珠郡能登町/2025.10.21 ©JPF |
 おいしいと評判の「ちょっこりカフェ『なごみ』」のメニューは、地元の料理好きのスタッフが中心に考案してすべて手作り ©PARCIC |
館内の畳部屋はキッズスペースとして活用されていて、こどもたちの遊び場のほか、おむつ替えや授乳ができるスペースも整えられるなど、利用者にとっての「使いやすさ」が丁寧に配慮されています。
また、施設内には、「もったいないコーナー」が設けられ、解体予定の家屋から取り出した洋服や食器などの再利用の場も多くの方に利用されています。
利用者の中には、
「被災後、卓球ができる場所がなくなっていたけれど、『なごみ』でまた仲間と集まれるようになってうれしい」
と話す方もおり、この場所が暮らしの再生に寄り添っていることがうかがえました。
 ちょっこりカフェ「なごみ」の様子/鳳珠郡能登町/2025.10.21 ©JPF |
 施設内の「キッズスペース」の様子/鳳珠郡能登町/2025.10.21 ©JPF |
 IKEAさんからご支援いただいたスリッパ/鳳珠郡能登町/2025.10.21 ©JPF |
 「なごみ」施設内には、解体予定の家屋から取り出した「もったいないコーナー」も/鳳珠郡能登町/2025.10.21 ©JPF |
「なごみプロジェクト」はあくまで期間限定の取り組みであり、能登町の今後の方針が定まるまでの“中継ぎ”の役割を担ってスタートしています。
必要とされている場であるからこそ、施設の継続的な運営や、地域へと無理なく引き継いでいくための仕組みづくりが今後の課題となります。
今後もPARCICとJPFは、地域の状況に寄り添いながら、安心して集える場を維持し、地元の人々による次のステップへとつなぐ支援を進めていきます。

PARCIC小栗さんとJPFスタッフ/鳳珠郡能登町/2025.10.21 ©JPF
能登現地レポートをもっと読む
▶ 地域の「あたたかいリビング」を支える~輪島市町野町「まちのの間」で続くコミュニティ支援~
▶ 「取り残される人をつくらない」ために~能登で続く支援と、復興に向けたこれからの課題~
今、知って欲しいJPF最新のお知らせ